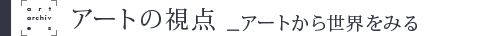工芸概念の形成を見るということは、美術概念の形成を見るということと切り離せぬ関係にある。
これは工芸概念の形成が美術概念の形成、さらに言うならばその自律と純化の産物として起こってきたからである。「美術」という概念は明治初期に西洋の概念を移植するために造語された翻訳語である。

ウィーン万国博覧会
その契機となったのは、1873年(明治6年)のウィーン万国博覧会であった。そのウィーン万国博覧会の出品目録には、「美術<西洋ニテ音楽、画学、像ヲ作ル術、詩学等ヲ美術ト云フ>」と記されており、今日で言うところの諸芸術の意で使われていたことが分かる。
そしてその後「美術」は現在の視覚芸術の意に絞り込まれていくわけだが、その過程において工芸概念が形成されていくことになるのだ。「美術」という語が官製翻訳語であることからも窺えるように、この時代は明治政府主導の下に作られてきたことなどから、官による制度という観点からその形成過程を見ていこうと思う。
システムとしての美術
1876年(明治9年)工部省、つまり工業を担う政府の官庁により美術学校(工部美術学校)が開設される。
ここではイタリア人教師により絵画、彫刻が教えられた。視覚芸術のみが美術学校の名の下に教授されたのである。このことは美術=視覚芸術として絞り込まれていく一つの契機になったといえよう。
混沌たる美術ジャンル
しかしまだまだこの時期「美術」は混沌たる状況にある。このことはその翌年開かれた内国勧業博覧会の出品目録とその出品物との関係にも見て取れる。「美術」部門は分類表の上で「彫像術」を筆頭とし、「書画」「彫刻及ビ石版術」「写真術」…という並びで6つに細分されている。その分類と実際の出品物との間には、今日の我々の認識とのかなりの相違を見ることができるのだ。
「書画」を例にとると、そこには花瓶等、絵が描かれているものならば何でも「書画」に分類され、「彫像術」についても、彫刻が施されていればすべて「彫像術」に、という分類がなされていた。しかも絵の類は「美術」部門と並ぶ「製造物」すなわち工業部門にも出品されており、今日の我々の認識からすると、まさに混沌たる状況であったといえるのだ。いうなれば各分野に工芸品が偏在している状態なのである。
それもそのはずで、「美術」の訳出の元になったのは現在の工芸を意味するドイツ語のKunstgewerbeであったのだ。そのため当時「美術」は実質的に工芸をさす語であり、それ故今日の我々からすれば「工芸」という枠の中に絵画、彫刻が存在するというような状況であったといえる。
この状況は1881年(明治14年)の第二回内国勧業博覧会の時点でもなんら変わりはなかった。ところが明治半ばごろを境に「美術」概念について純粋化の動きが起こり始める。
美術概念の純粋化と工芸の誕生
1882年5月にアーネスト・フェノロサが龍池会主催の講演会で絵画の優位性を論じ、また同年同月小山正太郎と岡倉天心が「書」が美術であるか否かをめぐり議論を交わしている。そしてそのような中、同年10月に第一回内国絵画共進会が開かれるのである。
この展覧会の規則は、西洋画法による絵画の出品と、パネル状の絵画以外の形態の出品を拒絶している。ここに絵画は平面表現としてより純粋な形態を追求し始めることになる。この会の審査委員長を務めた佐野常民は「夫レ絵画ハ美術ノ根本ナリ」と絵画の至上性を述べており、今日の絵画を頂点とする視覚芸術=美術のヒエラルキーをそこに感じ取ることができる。こうした純粋性、自立性追及の動きの中で行き場を失ったものの受け皿として「工芸」というものが生まれてくることになるのだ。
「美術工業」の誕生
そして1890年(明治23年)に開かれた第三回内国勧業博覧会で、ついに現在の「工芸」の基といえる「美術工業」なる語が見出される。ここに言う「美術工業」とは美術と工業にまたがる製造物ということで、規則では絵画、彫刻、建築、造園に属するもの以外で「殊に美術の精妙なる技巧を実用品に応用せるもの」と規定されている。
しかしここでこの内国勧業博では、現在絵画展ではなく工芸展で展示されている「漆絵」などの工芸的技法がまだ「絵画」に含まれていたことを付け加えておく。先の会が共進会の例と照らし合わせると、まだまだ社会全体の方向性が定まっていないことが分かる。
追いやられることで純粋化する工芸
さてこの「美術工業」という語は1895年(明治18年)の第四回内国勧業博において「美術工芸」と称されることとなり、同時に第三回内国勧業博まで「美術」となっていた部門名が「美術及美術工芸」と変えられ、現在「工芸」と呼ばれるこの「美術工芸」は「美術」から排除されてしまう。
また「絵画」の部では水彩、油彩、着彩など現在のスタンダードな絵画技法に絞り込まれた。1907年に開かれた文部省美術展覧会において、膠彩画を主とする「日本画」と油彩画を中心とする「西洋画」を絵画の枢軸とし、日本近代絵画の体制が確立する。この文展は、同時に視覚的純粋性を手に入れた絵画と彫刻に出品を限定し、その絵画・彫刻の純化の過程の中で行き場をなくしたものの受け皿として誕生した工芸を完全排除したのである。
工芸は視覚と間逆の位置にある触覚と不可分なものであり、美術=視覚芸術としようとする純化の中で排除されることとなったのだ。
その後1927年(昭和2年)に文展の後身である帝国美術院展覧会において「美術工芸」は再び復活し、官により美術への帰属を認められる。ここに美術ノ中で絵画を頂点とし、次に彫刻、そして工芸という現在のヒエラルキーが完成をみるのだ。
このようにして「美術」なるものの純化の過程の中で負の産物的に「工芸」という枠組みは生み出されてきたのである。