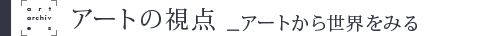言葉とは観念を表現する記号の体系であり、人はその言葉を用いて意思の疎通を行う。個々の記号、すなわち各々の言葉はある何物かを表意するわけだが、その表意内容のお互いの了承の基に意思の疎通は成立する。しかし世の中には数多くの言葉が存在しており、特に概念においてその表意内容が絶対性を持たず、あやふやに了解されているものが少なくない。『工芸』という概念もその一つである。
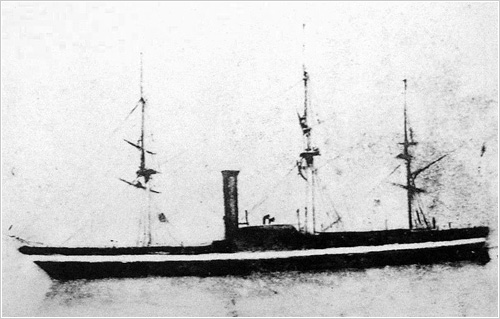
黒船来航による開国を以って、わが国には諸外国、とりわけ西欧文化の流入が起こりそれまで日本において存在しなかった概念が一気に押し寄せた。
『美術』という概念もその一つで、1873年に開催されたウィーン万国博覧会に関する明治政府の文書の中に翻訳語として初めて登場した。
この際、美術=視覚芸術とする西洋美術概念に基づいて、用の性格を持っていた『工芸』は美術とは区別されることとなった。
やがて行われたパリ万博(1900年)当時の臨時副総裁・九鬼隆一の以下の発言
「西洋においては、美術を純正美術と応用美術二科に分かち、甲には絵画、彫刻、建築を入れ、乙には金工、陶磁、織物など総て実用と美術を交うものを入る。則ち真の美術家と応用美術家とは全く別人にして、社会の品位自ら差等あり。」
から読み取れるように、「応用美術」=「工芸」が下位に位置づけされるべき美術分野として認識されている。以後今日に渡り、「工芸」に対する様々な解釈、動きが起こるわけだが、それらを大きく分けると次の三種に分類できよう。
一つ目が、個人主義、帝展派を中心とする近代主義的な個人の表現・主張の手段として「工芸」を捉えるもの、二つ目は民芸派による反近代主義的な、無欲無名の民衆による用の美・健康美の追求を目指すもの、そして三つ目が産業主義、すなわち大量生産によるデザインに傾向するものである。戦後に発足した青年作陶家集団、日本工芸会、日本デザイナーズクラフトマン協会、現代工芸美術家協会などの工芸界における動きを見ても、その解釈の多様さを見て取れるだろう。その後工芸と他美術ジャンルとの融合を目指したり、「工芸」に変わる新たな言葉の模索なども行われるが、いずれも不発に終わり今日も工芸概念の模索は続いている。昔の友と再会すると必ずこう聞かれる。「へぇー美大に行ってんのか!工芸科ってどんな事してんだ?」その度にいつも考える。私は「工芸」をどう捉えているのだろうか?
様々な流れの中の一つとして以下に鍛金という技術によって造形思考を展開し、作品を発表し続けている橋本真之氏の仕事を挙げてみる。
彼自身が代表作品と呼ぶ「果樹園」は曲面により構成された有機的なフォルムを持つ非常に大きな作品だ。通常鍛金という技術は制作中の作品を左手で持ち、木台の上に当て金と呼ばれる鉄の塊を差込み、どの上で金属板を叩いて作品を作るという方法が主であり、その性質上大きな作品を作るというのは困難なのである。しかし彼は自動車板金の人が使う当て盤と呼ばれる、手で持って使うこの出来る当て金のような鉄の塊を左手で持ち、それを使うで作品を大型化させた。曰く、固定して使う当て金よりもフレキシブルに動くことが可能となり、「運動」という作品と自分との存在形式を発見、肉体化することとなった、そうだ。実はこの作品はその発表のたびに大きくなっていて、成長・増殖し続けている。金属板を加工する鍛金という技術だからこそ生まれる内部空間のあるその形態、「動」というキーワードの基に生まれた更なる技術とそれによる作品の巨大化、さらには作家と作品とのあり方。技術、それは一つの素材と向き合い続けていく上で派生的に続いていく造形展開の軸となっており、工芸の本質のひとつである、というように捉える考え方がある。
「作品の表現のために技法を探すというのとは逆で、僕はガラスをいじっている間に不思議な感じのものが見つかっていく」と高橋禎彦さんはガラスという素材について述べている。工芸家と素材との関係の仕方、固有の素材と向き合い続ける中で作家の内面に発生してくる技術との関係性というところから、工芸の世界・作品が生まれてくるということなのだろう。それは彫刻家がまずカタチを決めそこから素材を選択するという造形方法にみられる素材との関係とは異なり、ひとつの素材と向き合い続ける事により派生的に生まれてくる関係性に「工芸」というものを見出せるといってよいだろう。
素材に共生する技術を幹とする一本の木。そこから派生してくる造形論。様々な解釈、流れを産み続け今もなおその生命活動が止むことのない「工芸」概念。「工芸」は「動」をその根底に置く生きた概念である、その本質にもまたその「動」を見出すことが出来る。人間理性中心主義の世界において曖昧な、確定性を持たない事項は存在できない。しかし情報の氾濫に加えて、近代化終焉による「個」の更なる台頭。世界は静かにだがものすごい勢いで変わってきている。これによりマイナーによる価値観・思想の多数存在という形式が出来上がり、それらはまた非常に流動的となるだろう。そんな新たな時代は、外形を変え、動き続ける生命体概念「工芸」の社会的台頭と、流動性をもつ事項が存在する、ということが普遍妥当的という客観性を持つことまで可能とするのではないかと思うのである。
なんて書いてみましたが、時代は何か難しいものを求めている状況ではないような気がします。人々は笑いを、癒しを渇望している。そんな気がします。そのような時代に表現は何を提案できるのか?それはすなわち表現者にとっては、作品によって生計を立てるにはどのような表現が求められているのか?ということになりますが、そのことを考える時、工芸概念について積極的に論じる余地を探すのは困難だと私は思います。