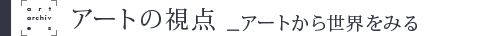credit: agushedem
credit: agushedem
その昔マルセル・デュシャンは「泉」という作品により、美術は美術館に置かれることにより成立するということを示した。またポップアートの第一人者 アンディー・ウォーホルは美術を美術足らしめるものは美術市場であると考えた。
日本において「美術」と「芸術」とは異なる概念であり、「美術」という語は制度的、歴史的に様々な問題を内包していることは北澤憲昭をはじめとする美術評論家の示すとおりである。
「美術」とは明治開国に際して、西洋の概念artの訳語として必要になったものであり、その実態は非常に制度的、政治的なものである。
しかしここでは美術=視覚芸術とし、その上位概念としての表現全般を示す語としての芸術という意味に限定し、芸術とは何であるか?ということについて考えることで、私の芸術に対する考え方を示してみたいと思う。
概念志向への非現実感
「芸術とは何であるか?」という命題は多くの人々が曖昧にしてきたものであり、一定の定義というものはない。
このことに関し徹底的に思考することは大変重要であり、意義深い。しかしあえて言うなれば、私自身にとってはリアリティーがない命題でもある。
私は鍛金という金属加工技法により作品を思考し制作している。この「工芸」という概念もまた美術同様非常にファジーなものであり、 その概念形成をめぐり様々な議論が起こる言葉である。実際「工芸」とはなんであるか、という命題は工芸に足を突っ込んでしまった誰もが必ず直面する問題であり、彫刻やデザインとの相違について思考せざるを得ない。
前述の北澤憲昭をはじめ、金子賢治、樋田豊次郎、等の工芸の評論家はもちろんの事、作家の側からの工芸概念提唱というものも多く、ジャンルとしての概念の議論というものはおそらく他のどの表現ジャンルよりも活発であるという認識を持っている。
私はこのような環境に身をおきながら自己の拠って立つ表現方法を模索していたのだが、いつの頃からか非常な違和感を覚えることになった。

![]() credit: Za Rodinu
credit: Za Rodinu
それはリアリティーのなさだ。
旧ソ連の崩壊が象徴するように先にロジックありき、型ありきという現実へのアプローチは得てして成功しないように思われる。なにか物事を決定付け、それに合わせて行動する、芸術の場合であれば芸術とは何かを決定した上でその芸術の概念に合わせて作品を制作するというベクトルは肉体性に欠けるためだと考える。
ここでいう肉体性とは個人の意思の深淵さに関わるもので、肉体性を伴わない、つまり自分にとっての生死に関わるような(必要に迫られるような)関心事でない事柄を表現することのリアリティーのなさからくる表現の弱さが表出するであろうと考える。
自明の事だが表現者は一人ひとり異なった人格を持つ。優れた表現者というものは例外なく自分の内の最大の関心事、欲求を知っており、それが故にそれを突き詰められるからこそ優れた表現をすることができる。
優れた表現者は外部の価値観に従っての表現など絶対にしない。自分にとって中途半端な関心欲求を徹底的に突き詰めることなど絶対にできない。外部の価値観に従って行動するのはビジネスマンの役目である。
多摩美工芸科では、陶、ガラス、金属の三コースに分かれている。工芸という名のもとに3つのコースがあるわけなのだが、この素材の違いは表現の方向性の根本的な相違を生み出しており、私はそれに気づいていた。全く表現の種類が違うにも関わらず、無理やり工芸という言葉のもとに三科を締め付けたような状況だった。
工芸とは何であるか?工芸とはこうあるべきだ、という議論渦巻く状況の中で工芸作品を作るということのリアリティーのなさに私は酷く違和感を覚えた。私は鍛金という金属加工技法により思考し作品を作っているのであって、空虚な工芸概念に基づいて作品を作っているわけではないことに気づいたのだ。陶やガラス、果ては木工から漆などの他素材の諸工芸はそれぞれに独特の表現思考を生み出し得ており、それらを一括に説明しうるような工芸という概念について考え作品を制作することは全く肉体性を持たない。これら諸工芸の作品を鑑賞し、これを包括するような説明を帰納的に考えることは重要だが、それを考えそれに基づき作品を制作することは空虚でありなんの意味も成さない。
これは芸術とは何であるか?という場合にも同様に当てはまる。
つまり芸術とは何であるか、ということを考えることは非常に重要だがそれは表現者にとっては実際上リアリティーがなく、意味をなし得ない。極言すれば表現者にとって、芸術とは何であるかということは必要ないということだ。
芸術とは何であるか?という命題は表現者以外の人間が、表現された作品を見てそこから帰納法的に考えるものであり、決して表現者が徹底的に思考するようなテーゼではないと私は考える。(もちろん芸術とは何であるか?ということが自らの肉体性を伴った最大の関心事であるような表現者にとっては別であるが)
芸術とは、現実のカオスの中から秩序を見出す、つまり言葉による世界の分節化と同じような種類のものであると思う。そのため永遠にボーダーラインが決定することないジャンルであり、それが故に面白いのだ。
須永 剛司氏の芸術についての考え方
レヴィ=ストロースのブ リコラージュ(bricolage)という概念をもってこの命題を以下に説明する。
世界は科学、すなわち概念の構造として説明された世界と、生活、すなわち知覚される出来事で満たされた世界により構成される。言い換えれば、世界は 概念構造とブリコラージュ(器用仕事)の二つの側面を持つといえる。この二者の中間に、その統合体として存在するのが芸術である。つまり作品に概念、意味、理論が付与されるとそれは芸術であるということだ。また、生活(出来事)を科学(概念)で振り返ることで芸術は生まれるとも言えよう。
この考え方を用いると、現代アートが難解であるという問いに対しては次のように説明できる。 結論から言えば、多くの現代アート作品の本質は、まずロジックありきでスタートし、それを下地にブリコラージュを引き寄せるという種類の表現であるため だ。概念構造、理論そのものを作品化するようなベクトルを強く持っている。つまり見るものに対して思考することを要求する。そのため感覚だけで作品を鑑賞 しようとする現代日本人には難解に見えるのだ。