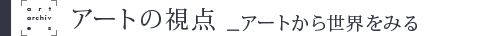我々日本人は言うまでもなく、日常生活における他愛もない会話から物事を深く思考するに至るまで日本語を使用している。当たり前であるということはそのことを理解しようとする機会を失わせ、そのことを疑うということからわれわれを遠ざけてしまうということだ。光のない場所に陰はない。日本という概念は外国という概念なしには誕生し得ないしまた存在し得ない。このことが示すように、ほぼ単一民族国家と言われる日本に暮らす日本人にとって、日本語というものはなかなか見えてこない。
『一般言語学講義』で知られるスイス人言語学者フェルディナン・ド・ソシュールによれば、言葉が存在する前に物事や観念は存在しないという。
例えば日本人が昨日駅弁を食べて、今日ほか弁を食べたとしよう。そしてアメリカ人が同じように昨日駅弁を食べ今日ほか弁を食べたとする。それは彼らからすれば「I ate a lunchbox yesterday. And I eat it too.」となり、違うものを食べたのだという意識は全くない。その言葉を知る人からすれば全く異なる二つの事象が(受ける感情も異なる)、その言葉を知らない人間にすれば何も変わらないのである。言葉は世界を創造し、その人間の認識、ものの見方を形成する要因となる。
社会的な習慣として定まっている意味に従って言葉が使われ、ある一連の対象にはある語が適用されるが、他の一連の対象には別な語を適用しなくてはならない―――こういう言葉の本質的な性格から、言葉には言葉による表現の対象となる外界の様々なものを「非連続的」な単位に「分節するという働き」―――つまり、あるものは同一の語で示されるから「同じ」、あるものは別の語で示されるから「違う」という風に分類するという働き―――があることが分かる。
では日本語は世界をどのように見る(分節化する)言語なのだろうか?一国語の語彙体系はその国民の文化の索引だといわれる。
ここでは語彙について、特に分節という観点から日本語の持つ特性、どのようにものの見方に作用するか、そして日本そのものについて、といったことを考察していこうと思う。そして言語そのものの本質に迫っていきたい。その前にまず日本語というものが何であるか、どういった性格を持つ言語であるのかについて見ていきたい。
日本語における方言とは、もはや外国語のようなものである
時枝誠記の『国語研究法』にこんなエピソードがある。時枝氏がパリに下宿していた時、フランス人である下宿の女将さんとスペイン人である下宿人が雑談をしていた。何気なしにその話を聞くと、スペイン語とイタリア語とでは話が通じるが、フランス語はこれらとは少し違う言葉だ、というようなことを話していたそうだ。
私自身大学ではイタリア語を少し学んだのであるが、母が学生時代スペイン語を専攻していてたまたま実家に帰省した折にイタリア語とスペイン語について色々と話したところ、あまりにも二つの言語が似ていることにびっくりした事がある。日本人は朝鮮語や中国語を耳にして、外国語とはああいう全然似ても似つかないものなのだと思っている。しかしヨーロッパあたりでは各国語の違いはそうたいしたものではないらしい。一人がデンマーク語をしゃべり、一人がスウェーデン語をしゃべり、もう一人がノルウェー語をしゃべり、それで互いに通じ合うという。日本で言えば、一人が東京の言葉で、一人が大阪の言葉で、一人が山口の言葉で話し合うようなものなのだろう。
事実日本語は方言の違いが激しい言語だといわれる。つまり「日本語」とはいうが、世界的に見れば実はそれは非常に多くの小言語の複合体であるのだ。英語、ドイツ語、オランダ語、デンマーク語などをひとまとめにしてゲルマン語などという。日本語はその全体がゲルマン語にも等しいものなのだ。
「肉」に関する語彙が豊富な西欧諸国
誰もが皆似たような記憶があるのではないかと思うが、中学に入り英語を習い始めびっくりしたことがある。それは家畜の分類の細かさだった。我々が「牛」というところを英語では、雌牛はcow、雄牛は去勢したものをox、しないものをbull、そして子牛をcalf、というように全然違った言葉で言い分ける。日本語であれば、雄の牛ならば雄+牛で雄牛、雌の牛ならば雌+牛で雌牛という二次的名だけなのに対して、一次的名、すなわち全く異なる言葉で分けているところに驚いたのだ。
要するに全く異なるものとして見ているということだ。イギリスその他のヨーロッパで牛を細かく言い分けるのは、イギリス人が昔から牛を飼い、ミルクを飲み、バターをなめ、牛の毛皮をはいで靴として履いたからに他ならない。だから日本語でも牛の飼養の盛んな地方にいくと、このくらいの言い分けは簡単にやってのける。例えば、広島県の辺りで雄牛をコトイといい、雌牛をオナメといい、子牛をベコというのはこれである。つまり生活に関係の深い事柄は詳しく言い分け、そうでないことは大雑把にしか言い分けないのだ。
「自然」とともに生きてきた日本人
このように、分類の数によってその国の生活様式、国柄が分かるものとして、日本語では雨の名前が挙げられる。日本語には時雨(しぐれ)、五月雨(さみだれ)、夕立、霙(みぞれ)・・・など雨の名前が多い。ことに梅雨と五月雨については同じ雨についていう語であるが、五月雨は雨そのものを指し、梅雨は五月雨の降る季節を指す。したがって五月雨は「やんだ」といい梅雨は「あけた」という細かい使い分けをする。
寺田寅彦によると他国語に訳せない日本語の例として「五月雨」「時雨」のほかに、「花曇」と「稲妻」があるという。風に関しても東風(こち)、野分(のわき)、木枯らし、凪(なぎ)などがあり、海岸地方に行けばその風向き、強さ、季節によりナライ、イナサなど極めて多くの風名を用いている。
とにかく日本では気象に関する語彙が多い。これは日本人が天候の変化の激しいこの国土に住みそれに順応する生活をしてきた結果とみていいだろう。小学校のころ夏休みの宿題の絵日記で天気を書く欄があったのは象徴的である。
日本語の代表的な語彙として挙げられるのが「水」である。
日本語の「水」は英語のwaterと違いその意味はごく狭い。すなわちそれは自然界の地上のものを表す点で特徴がある。それは涙や汗、雨の類を含まない。そして水は冷たいものをさし「湯」と対立する。ちなみに英語で「湯」はhotwaterの二語で表され、水の一種であるという認識が窺われる。「湯」の属性にいう「ぬるい」もまた日本的語彙のひとつである。
とある大学の日本語主任教授曰く、アメリカの学生には、「濁る」という日本語の意味がなかなか分からせにくい、そうだ。muddyという単語はあるが、これは日本語で言うところの泥水ぐらいにあたり、notcleanのように二語でなければ表せないという。水を尊重する日本らしい表現である。
水に関連してもうひとつ注意すべきは湿気に関した語彙である。ぬれる、湿る、しとる、潤う・・・などなど濡れ方に応じての語彙の分化は日本的といえよう。擬態語は元来日本に多くて有名だが、水に関するものだけでも、しっとり、じっとり、じめじめ、びしょびしょ、ぐしょぐしょ、びちょびちょ、じとじとなどいくらでもある。
自然に関するところだと鉱物、家畜、天体に関する日本語は乏しく、植物、魚に関する語彙が多いといわれる。「日本人で良かったな」と私がしみじみと思ってしまうのが、花が開くの意味に「咲く」、落ちるの意味で「散る」という表現があることだ。「咲く」という漢字をサクと読むのはいわゆる国訓で、中国語ではこの字はワラウと訓じる。英語のbloomは「花」という言葉の動詞化である。「散る」もそうで、中国では「散」という字は普通花には用いず、花がチルことは「落」で表す。英語でもfall(落ちる)である。
花の成長の変化に風情を感じてしまう日本人の心をこの「咲く」と「散る」という表現が物語っている。日本語が非体系的で、感傷的といわれるゆえんが窺える。
人に関するものとして有名なのが人体に関する語彙の少なさである。一般に身体部位の違いに対して日本人は極めて大まかである。極端なのはhandもarmも日本語では「手」といい、footもlegも「足」という点である。ひげに関しても中国語も英語も、日本語では二次的名でアゴヒゲ、クチヒゲ、ホオヒゲというところをそれぞれ一次的名で呼び分ける。外傷に関しても日本語では傷、怪我ぐらいのもので、英語ではwound、cut、bruise、scratch、などと使い分ける。
傷や病気に関して固有の名称の乏しい日本語に、死に関する名称の多いのは対照的である。これは命を重んじたというよりも、日本が有名な自殺国であることを物語る。ハラキリは日本語の中で最も早く世界中に広まった語として知られている。このハラキリの中にも、ツメバラ、オイバラなどの分類ができている。「心中」は森鴎外以来翻訳不能の日本語として知られている。同意語の「情死」も同様だ。加えて、「戦死」は英語に訳すとtobekilledと他動詞を受身形にすることで表現するが、これを日本語では「戦死する」という。この自動詞の形でいうところ、勇ましく悲しい。これら人体に関する語の少なさ、死に関する語の多さとその種類は、共同体を尊重し自己を一歩ひくという日本人の生き方を象徴するものとしてみることができる。
日本語にみる日本人の心理傾向
日本語では感情関係の語は実に豊富である。
気兼ねする、気が置けない、気まずい、気が引けるなど微妙な心理の動きを表す語彙が日本には多い。怒りだけを取り出してみても、起こる、憤慨する、腹が立つ、しゃくに障る、むしゃくしゃするなど、みな少しずつ意味が違う。字音語の中には、日本で古くできた日本製字音語というものがあるが、その中に心の動きを表すものが多いことは著しい傾向である。例えば、心配、懸念、無念、立腹、平気、本気、大丈夫、未練、存分、存外、案外、大儀、懸念、勘弁、会得、納得、承知、用心、辛抱、遠慮、覚悟、頓着などである。
日本人は心理状態を表す語の中で悲観的な面を見ることが多いというようなことを何かの本で読んだ気がする。曰く「幸せ」、「幸福」に関する語は、語彙数も使用頻度も少なく、反対の「苦労」、「不幸」の類が悲しい、哀れだ、さびしい、切ないなどとともに多く使われている、そうだ。
R・ベネディクトは『菊と刀』の中で、日本文化を恥辱感の文化と呼んだ。日本人にとって「恥をかかぬように」というのが毎日の行動を規定する根本精神である、と。それを反映して、恥辱感に関連した語彙が多い。恥ずかしい、決まりが悪い、みっともない、照れくさい、間が悪い、格好がつかない、引っ込みがつかないなどなど。思えばわれわれは他民族以上に日常些細なことに照れたり、間が悪がったりして暮らしているのかもしれない。
次に日本人特有の道徳意識から日本語特有の語彙が生じた例を挙げる。R・ベネディクトは、日本人のその地位にふさわしい振る舞いをすることに対する強い執着を指摘した。女の子は女の子らしくしなくてはならない、横綱であるからには堂々としてなければならないなどという言い回しがそれである。
私自身三人兄弟の長男で、よく親から「お兄ちゃんなんだから!」とか、「男の子でしょ!」といわれたものだ。今そのことを思うと、自分の人格形成にいかにそれらの言葉が大きく作用しているかがリアルに分かる。日本人はこの国独特の道徳観で自分たち自身を縛り上げ、窮屈に暮らしているのだ。副詞の中で「さすがに」は、ある地位にいる人物がその地位に相応しい行動をしたときに使うほめ言葉で、日本人好みの言葉である。「~しているだけあって」も同じような語感を持つ。反対にその地位に相応しくない振る舞いに対する非難を含む助詞には「くせに」があり、これも外国語に訳せない表現の一つである。
日本人は自分の長所を隠すことを良しとする。その独特の評価の結果、ゆかしい、奥ゆかしいという単語を持っているが、これが他国語には訳しにくい。関係の深い語彙に「たしなむ」がある。これはその効果があらわれるかどうかを問わず、人知れず用意をする意味で、よい意味で使われる。
言葉は世界を創造する
以上日本語の語彙についてみてきたわけだが、こうしてみてみるとおぼろげながら日本人像なるものが見えてくる。カオスである世界を言葉により分節化する。それはカオスである世界を言葉により秩序立てることである。カオス状態というものは認識することはできない。
しかし言葉により混沌から引き離された部分世界は我々の認識対象となる。言葉があるが故に我々は認識可能なのであり、言葉がなければ認識には至らない。さび、さび、風情という言葉があるから我々日本人はその事象を認識できるが、その言葉を持たない例えば西欧人はそれを認識できない。同様に自由という言葉しか持たない日本人にはliberty、freedomを理解できない。言葉は世界を創造する。異なる言語は異なる人間を作り出す。日本語を話すという当たり前のことは、我々を我々の知らないところで規定し制限しているのだ。